
このページでは、現在空き家を所有している方や、これから所有する方が知っておくべき、空き家に関連する法律や、それに付随する特例措置など、知っておくべき知識について紹介しております。
空家等対策特別措置法
概要
国会にて「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。この法律では、次のことが定められています。
- 空き家の実態調査
- 空き家の所有者へ適切な管理の指導
- 空き家の跡地についての活用促進
- 適切に管理されていない空き家を「管理不全空き家」「特定空き家」に指定することができる
- 「管理不全空き家」「特定空き家」に対して、助言・指導・勧告・命令等ができる
- 「特定空家」に対して罰金や行政代執行を行うことができる
管理必要理由
空き家を放置することにはリスクが高く、おすすめできません。なぜなら平成26年に国土交通省から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が交付されており、この法律によって空き家を放置することに大きなデメリットが発生するからです。そのため、空き家を所有している売主は、空き家にまつわる次のような状況を把握しておく必要があります。
空き家とは
そもそも「空き家」とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指します(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より抜粋)。具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされます。
たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることは不法侵入にあたるためできません。しかし、「空家等対策特別措置法」では、管理不全な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できる他、水道や電気の使用状況のインフラ情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなりました。
行政からの指示がないよう、定期的に所有している空き家の管理を行うことが重要です。もし万が一、適正管理に関する通達を受けてしまった場合は迅速に対応する意思を表示することが大切です。
適正管理不足の場合
適正管理の助言→指導→勧告→命令とは?
空き家を適正管理する義務は所有者にあります。建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。
「空家等対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
行政からの連絡は主に郵送で行われますが、管理状況に改善が見られなかったり、行政への連絡がなかったりした場合、行政職員が直接訪問するケースも多くあります。役所から所有している空き家の管理について、助言、指導、勧告、命令があった場合、直ちに役所の担当者へ連絡し、改善を行うという意思を伝える必要があります。
助言
例えば「庭の草木が伸びているので除草作業を行ってください」と行政から、適正管理を求める助言があった場合は、近隣住民からの苦情があったということがいえます。助言は法的な効力が無いため、対応するかどうかは所有者の判断に委ねられていますが、比較的容易に対応できることも多いため、近隣住民のためにも対応するようにしましょう。
指導
所有者が助言に従わない場合や、改善が直ちに必要な場合、所有者に対して市町村から空き家管理について指導されることがあります。指導は助言よりも行政指導として重く、所有者に対して適正管理を強く促すものです。
初めての行政指導で指導がされた場合、近隣住民から複数のクレームがあった可能性が高くなります。もし、所有している建物について市町村から改善の指示がきた場合、近隣住民のために、早急な管理状況の改善が必要です。具体的にどのように改善するか市町村にも連絡するようにしましょう。
勧告
空き家の適正管理について指導されても状況が改善されない場合、所有者に対して市町村は状況改善の勧告を行います。その状況は、近隣住民に大きな被害をもたらす可能性があるような深刻なケースも多く、一刻も早い対応が必要です。
- 「管理不全空き家」「特定空き家」に指定されてた後に改善を勧告されてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の税金6倍を支払う必要となります。
- もし、所有している空き家が管理改善の勧告を受けた場合、すみやかに担当者へ連絡し、現状を把握し改善する必要があります。勧告を受けた空き家は、そのまま放置すると危険なケースもあるため、迅速な状況把握と対応が必要となる深刻な事態だと認識してください。
※「管理不全空き家」「特定空き家」に指定されても、原因となっている状態を改善するとで「管理不全空き家」「特定空き家」から解除されます。
命令 (特定空き家のみ)
勧告されても所有者が対処しない場合、市町村は空き家の所有者に対して改善の命令をします。命令は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、行政処分と言われる行為で、空家等対策特別措置法では命令に背くと50万円以下の罰金(特定空き家のみ)が科されます。
また、命令を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」により、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体が行われる可能性もあります。
命令を受けた場合、それは行政からの最も厳しい通告だと思ってください。空き家をこのまま放置し続けると、建物の倒壊、火災の発生などで近隣住民の生命を巻き込む非常に高い危険性があり、一刻も早い迅速な対応が必要な状況です。もし管理状況改善の命令を受けた場合、すぐに職員に連絡し、空き家を適切に改善するような対応を取るようにしてください。
行政代執行 (特定空き家のみ)
行政代執行とは、所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。道路に越境している木の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したり、倒壊しそうな家屋を解体したりすることができます。何度も改善を要求しているにも関わらず所有者が対応してくれない場合、行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を取るというものです。
- ただし、これらの適正管理は本来、空き家所有者の責任です。行政代執行が行われるのは、緊急性が高いと判断された時のみで、行政代執行の費用は所有者に請求されることになります。
- 「放置しておけば行政が勝手に対処してくれる」と考えるのは間違っています。行政代執行は空き家所有者にとって全くメリットがないものだからです。
- 行政代執行を行う解体業者を選ぶのは行政職員です。彼らは最も安い会社を探して依頼するわけではありません。そのため、解体費用が比較的高額になってしまう傾向にあり、樹木の伐採やゴミ処分、建物の修繕についても同様です。
- 行政代執行の費用は税金です。行政代執行の費用は税金債務として扱われます。これは、行政代執行に要した費用の支払いがされない場合、税金と同様の回収が行われるということです。
- 税金を滞納した場合、役所は税金債務の回収を目的として、その人が所有する不動産を差押えて公売(行政による競売)にかけることができます。
所有者の同意は必要ありません。つまり、行政代執行が行われてしまった場合、その費用を支払わなければ所有している財産を勝手に売却されてしまうのです。この差押えされる財産は、行政代執行がされた空き家に限りません。今住んでいる自宅や乗っている車も差押さえることができます。
管理不全空き家と特定空き家とは何?
管理不全空家の概要
1年以上、誰も住んでいない状態の家で管理が不十分であり、今後もそのままの状態だと「特定空き家」に指定される恐れのある空き家を指します。
これまでの「空き家特別対策措置法」では、「特定空き家」だけの認定でしたが、「管理不全空き家」は「特定空き家」に指定される前段階の状態となります。
「管理不全空き家」は、あくまで空き家の管理を促すための措置であるのに対し、「特定空き家」は所有者に対して行政の直接介入するのが大きな違いです。
管理不全空き家の指定方法
「特定空き家」の認定の軽い状態。「特定空き家」の認定条件との違いがまだまだ曖昧というのが実情です。
- 認定基準
※管理不全空き家に指定される要因としては以下の4点が挙げられます。- 安全性が疑われる状態
- 環境や衛生に悪影響を及ぼしている状態
- 地域のコミュニティや不動産価格に悪影響とみなされる状態
- 犯罪数が増加する可能性
特定空き家の概要
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」で、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう』とされています。
特定空き家の指定方法
具体的にどのような状態だと「特定空家」に指定されてしまうのでしょうか。「特定空家等に対する措置」のガイドラインを元に、イラストを使用し分かりやすく説明します。もし、所有する空き家が「特定空家」に該当する場合は、近隣住民の方々に危険を及ぼす可能性があるので、一刻も早く、適切な管理をすることをお勧めいたします。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある (建築物が倒壊等するおそれがある。)
- 【基礎及び土台】
基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているかどうか、腐食又は蟻害によって土台に大きな断面欠損が発生しているかどうか、基礎と土台に大きなずれが発生しているかどうかなどを基に総合的に判断します。 - 【柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等】
構造を支える上で主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているかどうか、腐食又は蟻害によって構造を支える上で主要な柱等に大きな断面欠損が発生しているかどうか、柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断します。
- 【基礎及び土台】
- 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある (建築物が倒壊等するおそれがある。)
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある
- 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
- 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある
- ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている
- 景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。
- 景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている。
- 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。
- その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。
- 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
- 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。
- 敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。
- 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。
- 適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 立木が原因で、以下の状態にある。
- 立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている。
- 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。
- 空き家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。
- 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
- 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
- シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
- 建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。
- 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。
- 屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている。
- 周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。
- 立木が原因で、以下の状態にある。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく
保安上危険となるおそれのある状態- 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある (建築物が倒壊等するおそれがある。)
- 【基礎及び土台】
基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているかどうか、腐食又は蟻害によって土台に大きな断面欠損が発生しているかどうか、基礎と土台に大きなずれが発生しているかどうかなどを基に総合的に判断します。 - 【柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等】
構造を支える上で主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているかどうか、腐食又は蟻害によって構造を支える上で主要な柱等に大きな断面欠損が発生しているかどうか、柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断します。
- 【基礎及び土台】
- 建築物が著しく保安上危険となるおそれがある (建築物が倒壊等するおそれがある。)
- そのまま放置すれば著しく
衛生上有害となるおそれのある状態- 建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある
- 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
- 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある
- ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある
- 適切な管理が
行われていないことにより
著しく景観を損なっている状態- 適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている
- 景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。
- 景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている。
- 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。
- その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。
- 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
- 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。
- 敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。
- 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。
- 適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている
- その他周辺の
生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態- 立木が原因で、以下の状態にある。
- 立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている。
- 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。
- 空き家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。
- 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
- 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
- シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。
- 建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。
- 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。
- 屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている。
- 周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。
- 立木が原因で、以下の状態にある。
罰則
「管理不全空き家」「特定空き家」に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。
さらに「特定空き家」に限っては自治体からの「助言」→「指導」→「勧告」→「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。
デメリット
土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
固定資産
「管理不全空き家」「特定空き家」に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、上述の通り、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。
住宅用地の特例措置が適用される場合と、されない場合とでは以下のように固定資産税額が変わってきます。とても大きな金額差が生じますので、ご注意ください。
【例】
空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が【建物】500万円【土地】2000万円だった場合
住宅用地の特例措置が適用される場合
(通常の土地、建物にかかる固定資産税額)
| 課税標準額 | 税率 | 金額 | |
| 建物 | 500万 | 1.4% | 7万 |
| 土地 | 2000万 ×1/6 (住宅用地の特例措置による減額) | 1.4% | 4.7万 |
| 合計 | 11.7万 | ||
住宅用地の特例措置が適用されない場合
(自治体から「勧告」を受けた「管理不全空き家」「特定空き家」にかかる固定資産税額)
| 課税標準額 | 税率 | 金額 | |
| 建物 | 500万 | 1.4% | 7万 |
| 土地 | 2000万 | 1.4% | 28万 |
| 合計 | 35万 | ||
上記の場合、自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額は、通常よりも年間23.3万円高額になることが分かります。

お気軽にご相談ください。
ハピネスホーム管理へ
お任せください。
メール・お電話での
お問い合わせはこちら


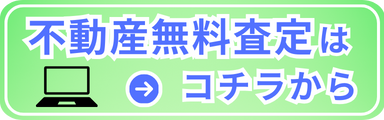



 kocchan0424@gmail.com
kocchan0424@gmail.com