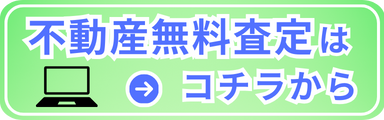「空き家について調べているけれど、実際にどんな問題が起きていて、行政はどう対応しているの?」――そんな疑問をお持ちではありませんか?
空き家の増加は、治安の悪化や景観の損失、災害リスクの上昇など、地域社会にさまざまな悪影響を及ぼす深刻な課題です。特に神奈川県では、都市部と郊外の両方で空き家問題が顕在化しており、自治体ごとの取り組みも注目されています。
この記事では、神奈川県の空き家問題の現状を明らかにしつつ、行政がどのような対策を講じているのかを5つの事例に分けて紹介します。
空き家に関心のある方、将来の対策を考えている方にとって、有益なヒントが見つかるはずです。
空き家問題とは?基礎知識と現状の把握

空き家の定義とは?
「空き家」とは、基本的に人が住んでおらず、一定期間利用されていない住宅を指します。総務省の定義によれば、住宅・土地統計調査において「常に人が住んでいない住宅」を空き家とし、賃貸用や売却用の住宅も含まれます。特に問題とされるのは「その他の空き家」と呼ばれる、管理されていない放置空き家です。これらは老朽化が進みやすく、周辺地域にさまざまなリスクをもたらします。
※「空き家」の分類について・・・詳しくはコチラ(参照:日本空き家サポート)
なぜ空き家が増えているのか?
少子高齢化や都市部への人口集中が空き家増加の大きな要因です。相続によって住宅を所有する人が増える一方で、その物件を活用する意欲や手段がないケースが目立ちます。また、住宅ローンの完済後も高齢の所有者が住み続け、亡くなった後に管理されなくなるケースも増加しています。不動産市場での需要と供給のミスマッチも問題を複雑にしています。
空き家がもたらす社会的・経済的な影響
空き家は倒壊や火災、不法侵入のリスクを高めるだけでなく、周囲の景観や土地の価値にも悪影響を与えます。地域コミュニティの活力低下にもつながり、行政コストの増加も無視できません。さらに、長期間放置されることで解体費用や修繕費がかさみ、将来的な活用も難しくなります。
神奈川県における空き家の実態
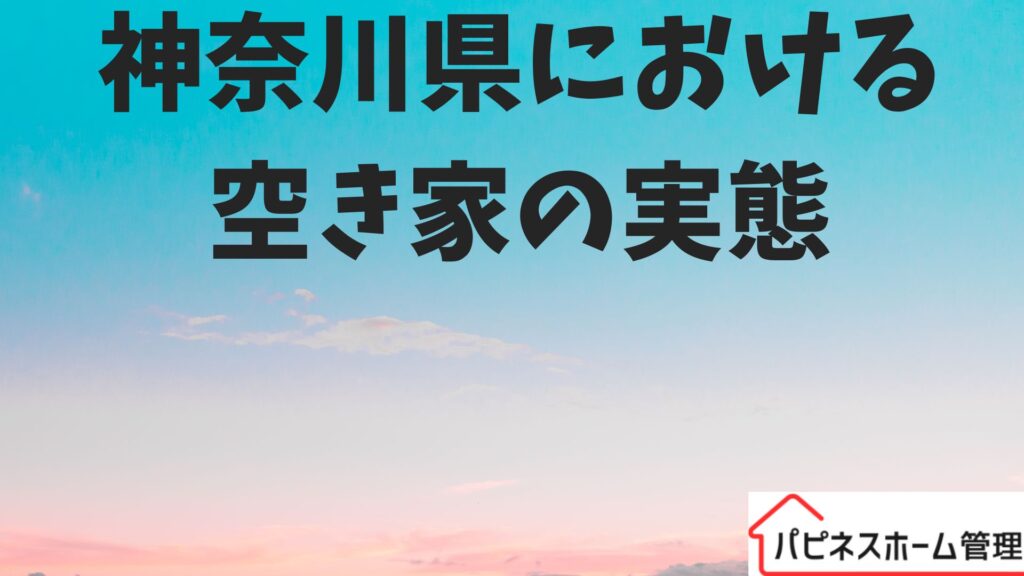
地域別に見る空き家の分布と特徴
神奈川県では、横浜や川崎など都市部に比べて、相模原市や秦野市、三浦市などの郊外・山間部で空き家率が高くなっています。交通アクセスや生活インフラの利便性によって地域差が生じており、利活用が難しいエリアでは放置空き家が目立ちます。
※神奈川県の空き家率(令和5年度)・・・詳しくはコチラ(参照:神奈川県庁)
神奈川県内で特に深刻なエリアはどこか?
三浦半島の一部や丹沢山系に近いエリアでは、過疎化が進み空き家の増加が顕著です。これらの地域では人口流出が続いており、空き家の利活用や流通が滞っているため、行政による積極的な介入が求められています。
空き家所有者が抱える主な悩みとは?
空き家を所有する人々の多くは、管理の手間やコスト、相続の問題に頭を悩ませています。特に遠方に住んでいる所有者にとっては、現地での確認や対応が困難であり、税金や修繕費用の負担が重くのしかかっています。
※神奈川県 横須賀市の空き家管理最新事情・・・詳しくはコチラ(参照:ハピネスホーム管理)
神奈川県の行政による空き家対策5選
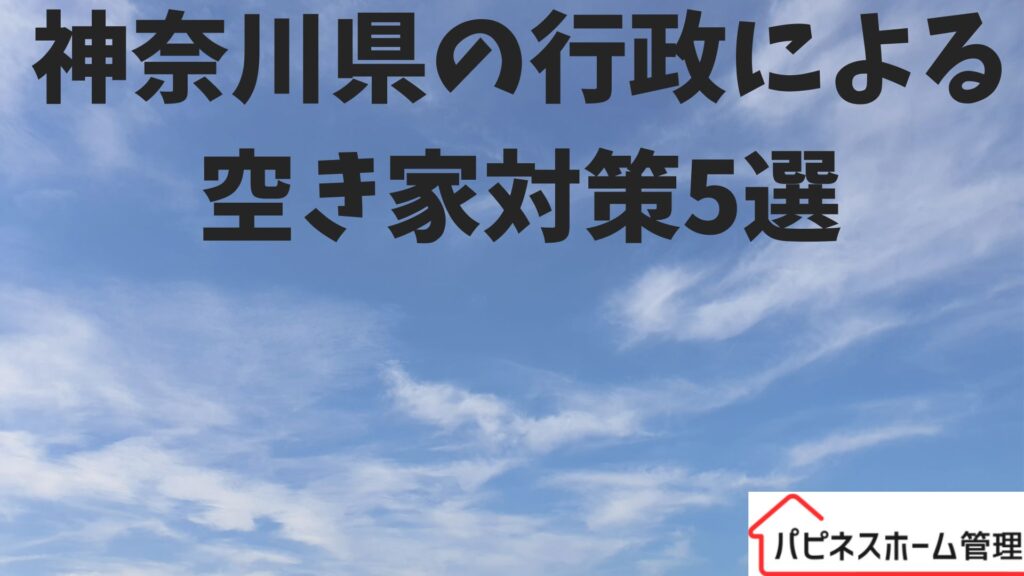
空き家バンク制度の活用と効果
神奈川県内の複数の自治体では、空き家バンクを通じて物件情報を公開し、買い手や借り手とマッチングを図っています。登録数は徐々に増加しており、地域活性化や移住促進にもつながる仕組みとして注目されています。
※神奈川県横浜市の空き家マッチング・・・・・詳しくはコチラ(参照:横浜市役所)
※神奈川県横須賀市の空きバンク・・・・・・・・詳しくはコチラ(参照:横須賀市役所)
※神奈川県逗子市の空きバンク・・・・・・・・・・詳しくはコチラ(参照:逗子市役所)
※神奈川県葉山町の空きバンク・・・・・・・・・・詳しくはコチラ(参照:三浦郡葉山町役場)
解体・撤去に対する補助金制度
老朽化した空き家の撤去を促進するために、解体費用の一部を補助する制度も整備されています。特に倒壊の危険がある建物や、近隣への影響が大きいと判断された場合には、迅速な対応が行われています。
リノベーション支援や活用事例
空き家を住居や店舗、シェアハウスなどにリノベーションする取り組みも進んでいます。補助金や技術支援を受けながら再利用される事例が増えており、地域の魅力向上にも寄与しています。
税制優遇と固定資産税の見直し
空き家の適切な管理や利活用を促すために、一定の条件を満たせば固定資産税の優遇措置が適用されるケースがあります。逆に、放置されたままの空き家にはペナルティ的な課税が行われることもあります。
※空き家と固定資産税の関係・・・詳しくはコチラ(参照:ハピネスホーム管理)
空き家対策条例とその運用状況
県内の多くの市町村では独自の空き家対策条例を設けており、立ち入り調査や勧告、命令といった段階的な措置を通じて、空き家の管理を強化しています。法的根拠に基づく対応が可能となり、実効性が高まっています。
空き家問題の今後と市民にできること
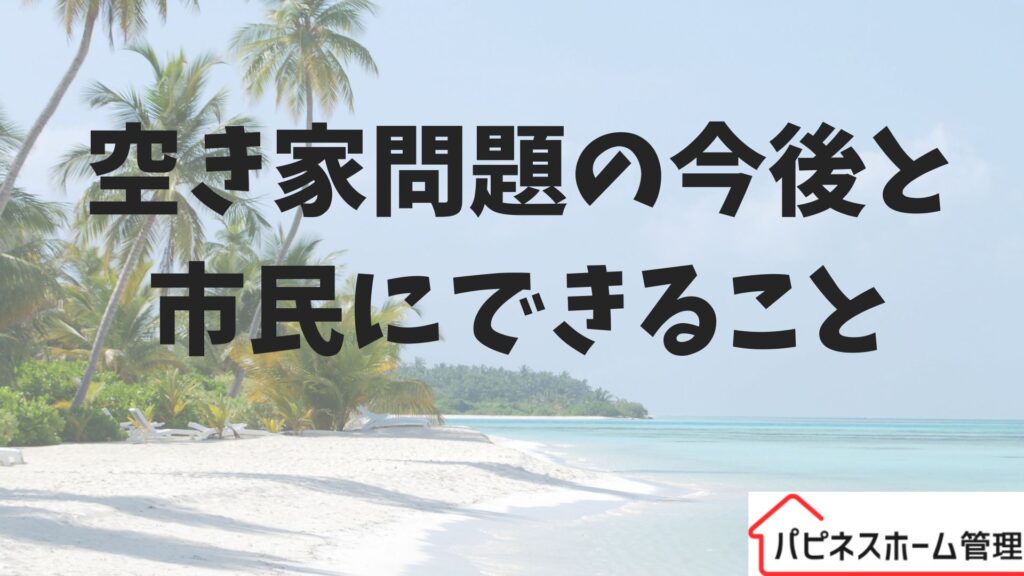
空き家の活用方法とアイデア
空き家は住まいとしてだけでなく、カフェやコワーキングスペース、地域交流拠点としても活用できます。発想の転換により、新たな価値を生み出すことが可能です。民間企業やNPOと連携した取り組みも増えています。
※神奈川県 葉山町の空き家活用・・・・・詳しくはコチラ(参照:葉山町役場)
※神奈川県 横須賀市の空き家活用・・・詳しくはコチラ(参照:横須賀市役所)
所有者としての責任と対応策
空き家を所有することは、単に財産を保有するだけでなく、地域の安全や景観にも責任を持つことを意味します。定期的な点検や登記の見直し、売却・貸し出しといった具体的な対応が求められます。
※地域密着型の空き家管理は「ハピネスホーム管理」・・・詳しくはコチラ
(管理地区:神奈川県 横浜市・横須賀市・逗子市・葉山町、大阪府 堺市・高石市・枚方市、京都府 八幡市・木津川市・相楽郡、奈良県 生駒市)
地域住民や自治体との協力の重要性
空き家問題は個人の問題ではなく、地域全体で向き合うべき課題です。地域住民同士が連携し、自治体と協力することで、スムーズな対応と持続可能なまちづくりが実現します。
まとめ:神奈川県の空き家問題から学ぶ持続可能な地域づくり

行政と市民が連携して取り組む意義
神奈川県の取り組みから見えてくるのは、行政だけでなく市民一人ひとりの関与が空き家問題解決の鍵であるということです。お互いの役割を明確にし、共に行動することで初めて成果が生まれます。
他地域への応用可能な成功事例の紹介
空き家バンクや補助金制度、条例の活用といった施策は、神奈川県以外の自治体でも応用が可能です。成功事例を共有し、他地域でも同様の対策を導入することで、全国的な空き家問題の改善に寄与できるでしょう。